 |
 |
 |
 |
第18回鎌倉検定試験2級
《歴史・旧跡の問題》
|
|
| 歴史・旧跡に関する記述について,最も適当なものを 1 ~ 4 から選びなさい。 |
| (1) | 「天平五年」(733年)と記された木簡が発見され,鎌倉郡衙の所在が確認されるきっかけとなった遺跡はどこか。 |
| 1 長谷小路周辺遺跡 2 台山藤源治遺跡 3 今小路西遺跡 4 水道山戸ヶ崎遺跡 |
| 御成小学校周辺は、1979年(昭和54年)の発掘調査によって、半地下式倉庫跡や天平5年(733年)の銘が入った木簡が発見され、鎌倉郡衙の遺構と考えられています。
近年の調査では、大規模な建築遺構群などが発見され、鎌倉幕府の有力御家人・安達泰盛の屋敷跡の可能性があるのだとか。 |
答 3

| 今小路西遺跡の発掘調査で、半地下式倉庫跡とともに発見された木簡。 |
| (2) | 平家方の武将だった梶原景時が,源頼朝の信任を得るきっかけになった戦いは何か。 |
| 1 富士川合戦(富士川の戦い) 2 石橋山合戦(石橋山の戦い) 3 屋島合戦(屋島の戦い) 4 一ノ谷合戦(一ノ谷の戦い) |
| 1180年(治承4年)8月、以仁王の令旨を受けて源頼朝が挙兵すると、梶原景時は一族で平家方の大庭景親に与しますが、石橋山の戦いに敗れて山中に隠れ潜む頼朝を見逃したとされています。 |
答 2
(湯河原町)
| 湯河原町のしとどの窟は、石橋山の戦いに敗れた頼朝が隠れ潜んでいたという巌窟。 |

 |
 |
 |
 |
 |
 |
| (3) | 3代執権北条泰時のころの鎌倉の四境のうち,北の境はどこか。 |
| 1 常盤 3 稲村 |
2 山内 4 長谷 |
| 1224年(元仁元年)12月26日、三代執権北条泰時は、鎌倉に疫病が流行したことから、六浦、小坪、稲村、山内の四境(鎌倉の境界(外側))で「四角四境祭」を執行させています。 「四角四境祭」とは、陰陽道に基づく除災の儀式。 |
答 2
| 四角四境祭の山内の斎場は八雲神社だったと伝えられています。 |
| (4) | 北条時宗が幼少であったため,眼代として執権を務めたが,蒙古襲来の国難に際して執権を退き,再び連署となって時宗を補佐した人物はだれか。 |
| 1 北条重時 3 北条長時 |
2 北条政村 4 北条経時 |
| 五代執権北条時頼は執権の座を退くと、その職を北条重時の子長時に譲ります。 これは嫡子の時宗が幼少であったための措置で、長時は時宗の代理としての就任でした。 長時が執権を辞した後は、一族の長老で連署だった北条政村が執権に就任。 この措置も、まだ14歳だった時宗の代理。 そして、蒙古襲来の危機に時宗が八代執権に就任すると、政村は再び連署となっています。 |
答 2
| 北条氏常盤亭は、第七代執権北条政村をはじめとする北条氏(政村流)の別邸。 |

| (5) | 次のうち,初代の関東管領に任じられた人物の組み合わせはどれか。 |
| 1 高師直・上杉氏憲 2 高師冬・上杉氏憲 3 高師直・上杉憲顕 4 高師冬・上杉憲顕 |
| 関東管領は、室町時代に鎌倉府の長官だった鎌倉公方を補佐するために置かれた役職。 当初は関東執事と呼ばれ、足利尊氏の嫡子義詮が鎌倉を統治していた頃には斯波家長・上杉憲顕・高師冬・高重茂が就任しています。 |
答 4
| (6) | 『海道記』によれば,櫓の屋根に「玉の瓦」や「金の盤・雁灯」など,豪華な飾りが施されていたと,往時の姿が記されている旧跡はどこか。 |
| 1 勝長寿院 3 太平寺 |
2 永福寺 4 東勝寺 |
| 『海道記』に・・・ 「重なる櫓には、玉の瓦、鴛の翅を飛ばし、両目両足の並び給える臺には、金の盤、雁燈をかかげたり」 『東関紀行』に・・・ 「二階堂は殊にすぐれたる寺なり。鳳の甍、日にかがやき、鳧の鐘霜にひびき、楼台の荘厳よりはじめて、林池のふもとにいたるまで、ことに心とまりて見ゆ」 と記されているのは永福寺。 |
答 2
| 永福寺は、源頼朝が奥州平泉の中尊寺・毛越寺・無量光院などを模して建てた寺院。 |
| (7) | 鎌倉十井のうち,徳川光圀の『鎌倉日記』に「…谷ノ辺ニ潔キ水涌出ル也」と書かれているのはどれか。 |
| 1 星ノ井 3 鉄ノ井 |
2 泉ノ井 4 扇ノ井 |
| 泉井谷の辺に潔き水涌出る也。 |
答 2

| 泉ノ井は、浄光明寺の先にある潔き水が涌出る井戸。 |
| (8) | 源頼朝について,次の説明文で内容に誤りを含むものはどれか。 |
| 1 | 『吾妻鏡』によれば,1180年(治承4),鎌倉に入った源頼朝は大倉御所に移り,東国武士たちから「鎌倉の主」と仰がれるようになった。 |
| 2 | 源頼朝は,御家人を統率する侍所,一般政務・財政事務を担当する公文所,訴訟を担当する問注所を設置し,鎌倉を本格的な政権所在地として整備した。 |
| 3 | 源頼朝は,由比若宮を大倉郷に遷し,鶴岡八幡宮として,町の中心に据えて若宮大路を整備した。 |
| 4 | 源頼朝は,父義朝の菩提を弔うために勝長寿院を,内乱の戦死者を鎮魂するために永福寺を建立した。 |
| 源頼朝が由比若宮を遷した地は、大倉郷ではなく小林郷。 |
答 3

| 由比若宮は、頼朝の先祖頼義が石清水八幡宮を勧請して創建しました。 |
 |
(大倉御所跡) |
| 鶴岡八幡宮・勝長寿院・永福寺は、頼朝建立の三大寺院と呼ばれています。 |
| (9) | 仮粧坂について,次の説明文で内容が正しいものはどれか。 |
| 1 | 七里ヶ浜,腰越,片瀬を経て東海道へ通じる鎌倉・京都往還の出発点であった。 |
| 2 | 国指定史跡であり,「大切岸」や「平場」など,複雑な防御の跡が残されている。 |
| 3 | 国指定史跡であり,鎌倉の東側の守備と考えられ,「鎌倉七口」のなかで当時の姿を最も伝えている。 |
| 4 | 武蔵方面に通じる戦略上極めて重要な拠点であったことは,新田義貞が鎌倉攻めの際に,主力を向けたことで伺える。 |
| 鎌倉七口の一つ仮粧坂を越えると藤沢・戸塚を経て武蔵へ通じます。 逆に鎌倉へ入ると武蔵大路、窟小路を経て鎌倉の中心部へ通じています。 1は極楽寺切通、2は名越切通、3は朝夷奈切通の説明。 |
答 4
| 1333年(元弘3年)5月18日、新田義貞は隊を三隊に分け、本隊は仮粧坂、大舘宗氏と江田行義の部隊は極楽寺坂、堀口貞満、大島守之の部隊が巨福呂坂から鎌倉に攻め入りました。 |

| 歴史・旧跡について関連あることがらの組み合わせとして誤っているものを 1 ~ 4 から選びなさい。 |
| (10) | 人物と墓所の所在地 |
| 1 大江広元-明王院裏山 2 梶原景時-朝夷奈切通 3 木曽義高-常楽寺裏山 4 上杉憲方-極楽寺坂 |
| 朝夷奈切通には、梶原景時に暗殺された上総広常の五輪塔があります。 |
答 2
| 明王院裏山の五層塔は、大江広元の墓と伝えられています。 広元の墓は、西御門の法華堂跡にもあります(大江広元墓)。 上総介塔は、上総広常のものといわれています。 |
 |
| 常楽寺裏山の木曽塚は、源頼朝に討たれた木曽義高の首塚。 極楽寺坂(西方寺跡)にある七層塔は、上杉憲方の墓と伝えられています。 明月院の明月院やぐらも憲方の墓と伝えられています。 |
| (11) | 橋と関連人物 |
| 1 | 歌ノ橋-渋川刑部六郎兼守 |
| 2 | 針磨橋-我入道 |
| 3 | 乱橋-足利尊氏 |
| 4 | 裁許橋-西行 |
| 乱橋は、新田義貞が鎌倉に攻め入ったときに、北条軍が乱れ始めた場所といわれています。 |
答 3
 |
 |

| 歴史・旧跡について,次の説明文の〔 〕に最も適当なものを 1 ~ 4 から選びなさい。 |
| 北条時頼は〔 (12) 〕により三浦一族を滅ぼし,北条氏の権力を強めた。それまでの摂家将軍を廃して,新たな将軍として皇族から,後嵯峨上皇の皇子〔 (13) 〕親王を迎えた。 執権の補佐役として連署を復活し〔 (14) 〕を任命,ますます増える所領をめぐる御家人の訴訟を効率よく裁くため引付を設けるなど政治組織を整備した。 また,禅の本格的修行場としての〔 (15) 〕を建立して,武家の気風にふさわしい禅宗の発展に尽くした。 時頼の廟所は〔 (16) 〕境内にある。 |
| (12) |
| 1 承久の乱 2 二月騒動 3 宝治合戦 4 霜月騒動 |
| (13) |
| 1 宗尊 2 惟康 3 久明 4 守邦 |
| (14) |
| 1 北条重時 2 北条時房 3 北条政村 4 北条義時 |
| (15) |
| 1 浄妙寺 2 建長寺 3 円覚寺 4 浄智寺 |
| (16) |
| 1 建長寺 2 常楽寺 3 明月院 4 円覚寺 |
| 北条時頼は、1246年(寛元4年)、深秘の御沙汰(北条得宗家の秘密会議)で、病気の兄経時に代わって執権となりました。 この年の宮騒動で四代将軍の藤原(九条)頼経を鎌倉から追放。 翌1247年(宝治元年)、三浦泰村を滅ぼし(宝治合戦)、北条重時を連署とします。 1249年(建長元年)には、評定衆の下に引付を設置して御家人の所領争いの裁判の迅速化を図りました。 1252年(建長4年)、五代将軍藤原頼嗣を廃し、後嵯峨上皇の皇子宗尊親王を六代将軍に迎えます。 翌1253年(建長5年)、建長寺を創建。 1256年(康元元年)には執権を退きますが、実権は握り続けました。 1263年(弘長3年)11月22日、最明寺で死去。 |
答
| (12) 3 (13) 1 (14) 1 (15) 2 (16) 3 |
 |
 (明月院) |
| 建長寺は、北条時頼が宋の蘭渓道隆を招いて開いた日本で初めての「禅専門道場」。 明月院は時頼が建立した最明寺を前身として八代執権北条時宗が創建した禅興寺の支院。 境内には時頼の墓が建てられています。 |

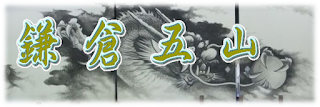
| 〔 (17) 〕やぐらは鎌倉に現存するやぐらの中で最も大きい。壁面には基壇が設置され, 壇上に〔 (18) 〕如来,〔 (19) 〕如来が浮き彫りされている。基壇上部に十六羅漢像の浮き 彫りがあり,このやぐらが「羅漢洞」といわれるゆえんとなっている。関東管領の〔 (20) 〕 の墓所と伝えられ,中央には宝篋印塔が祀られている。 |
| (17) |
| 1 日月 2 朱垂木 3 明月院 4 百八 |
| (18) |
| 1 薬師 2 大日 3 阿弥陀 4 釈迦 |
| (19) |
| 1 多宝 2 阿閦 3 定光 4 宝生 |
| (20) |
| 1 上杉憲顕 2 上杉憲実 3 上杉憲方 4 上杉氏憲 |
| 鎌倉に現存する「やぐら」で最も大きいのは明月院やぐら。 やぐら内の宝篋印塔は、山内上杉家の上杉憲方のものと伝えられています。 宝篋印塔背後の壁面には釈迦如来、多宝如来が浮き彫りされ、その周りに十六羅漢の浮き彫りもあるため「羅漢洞」とも呼ばれています。 |
答
| (17) 3 (18) 4 (19) 1 (20) 3 |
 |
| 明月院やぐらは、平治の乱で討死した首藤俊通のもともいわれますが定かではありません。 2023年(令和5年)、京都にあった経俊の父俊通の墓が明月院内に改装されています。 |
| 自然・景観の問題 |

第18回2級トップ

(3級・2級・1級の問題と解説)
| ★鎌倉検定の受検お申し込みは 鎌倉商工会議所ホームページへ |
(鎌倉情報トップ)
|
|