 |
 |
 |
 |
第18回鎌倉検定試験2級
《寺院・神社の問題》
|
|
| 寺院・神社に関する記述について,最も適当なものを 1 ~ 4 から選びなさい。 |
| (36) | 開山として南洲宏海,大休正念,兀庵普寧の三人が名を連ねる寺はどこか。 |
| 1 浄妙寺 2 瑞泉寺 3 浄智寺 4 圓應寺 |
| 浄智寺の開山に招かれたのは南洲宏海でしたが、任が重いとして大休正念を迎えて入仏供養を行い、既に世を去っていた兀菴普寧を開山としたことから、三人の名が連ねられているらしい。 |
答 3

| 浄智寺は、北条宗政の菩提を弔うために創建されました。 開基は宗政の子師時。 創建がいつなのかは諸説あるようですが、宗政が亡くなったのは1281年(弘安4年)。 師時が6歳くらいの頃。 師時の母が、まだ幼い師時を開基として創建したのだろうと考えられているようです。 |
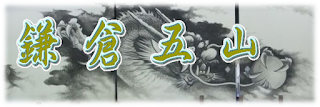
| (37) | 鎌倉時代の「鎌倉」地区を示す唯一の絵図である「浄光明寺敷地絵図」が描かれた目的は何か。 |
| 1 | 鎌倉幕府の滅亡後に,寺領を保護してもらうため。。 |
| 2 | 鎌倉幕府の新しい執権に,寺領を認めてもらうため。 |
| 3 | 鎌倉幕府の新しい将軍に,寺領を保護してもらうため。 |
| 4 | 鎌倉幕府が開かれた際に,寺領を認めてもらうため。 |
| 浄光明寺敷地絵図は、鎌倉幕府の滅亡後に寺領を保護してもらうために描かれたもの。 |
答 1

| 浄光明寺敷地絵図は、鎌倉時代末から南北朝時代にかけての浄光明寺の境内の建物・寺域や周辺の景観・屋敷などを詳細に伝えるもの(重要文化財)。 |
| (38) | 三体あるうち二体が国の重要文化財になっている,杉本寺の本尊は何か。 |
| 1 阿弥陀如来像 2 十一面観音像 3 千手観音像 4 薬師如来像 |
| 杉本寺は坂東三十三所第一番の観音霊場。 本尊は行基・慈覚・恵心の十一面観音像。 |
答 2

| 杉本寺の観音堂内陣中央の十一面観音は、比叡山延暦寺の横川、浅草寺、中尊寺、毛越寺などを開いた慈覚(円仁)の作(重要文化財)。 右の十一面観音は、花山天皇の発願によって恵心僧都が彫ったもの(重要文化財)。 左の十一面観音は、杉本寺開山の行基の作と伝えられています。 |

| (39) | 鎌倉十三仏詣の霊場のうち,浄妙寺に祀られているのは何か。 |
| 1 文殊菩薩 2 弥勒菩薩 3 虚空蔵菩薩 4 釈迦如来 |
| 浄妙寺の本尊は釈迦如来。 三途の川のほとりでは、釈迦如来の化身・初江王の裁判を受けます。 |
答 4
| 浄妙寺は、鎌倉十三仏第二番の霊場。 |

| (40) | 桜田門外で大老井伊直弼を襲撃した水戸浪士の一人,広木松之助がかくまわれ,後日,その境内で切腹して果てたといわれ,境内に墓がある寺はどこか。 |
| 1 教恩寺 2 大寶寺 3 常栄寺 4 上行寺 |
答 4
| 鎌倉に落ち延びてきた広木松之介は、材木座の源七という魚仲買人の家に身を寄せていましたが、人の出入りが多い家で安全ではないことから、上行寺で匿ってもらうことになったのだとか。 1862年(文久2年)3月3日、上行寺で切腹。 |
| (41) | 鎌倉七福神のうち,福禄寿を祀られている社寺はどこか。 |
| 1 鶴岡八幡宮 2 妙隆寺 3 本覚寺 4 御霊神社(坂ノ下) |
| 鶴岡八幡宮は弁財天、妙隆寺は寿老人、本覚寺は夷尊神。 御霊神社の9月の例祭では、福禄寿が参加する面掛行列が行われます。 これにちなんで、宝物庫には福禄寿が安置されています。 |
答 4

| 御霊神社の9月の例祭では、福禄寿が参加する面掛行列が行われます。 これにちなんで、宝物庫には福禄寿が安置されています。 |

| (42) | 日本最大級の木造仏像である長谷寺の十一面観音菩薩像に金箔を施したと伝えられている人物はだれか。 |
| 1 源頼朝 2 足利尊氏 3 藤原房前 4 足利義満 |
| 長谷寺の本尊・十一面観音像の金箔は足利尊氏が施し、光背は足利義満が納めたと伝えられています。 |
答 2

| 長谷寺は坂東三十三所第四番の観音霊場。 本尊の十一面観音は、大和国長谷寺の十一面観音と同じく、右手に錫杖を左手に蓮華の花瓶を持ち、蓮華座ではなく岩座に立つことから「長谷寺式十一面観音」と呼ばれています。 |

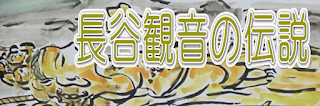
| (43) | 荏柄天神社にある「かっぱ筆塚」の石碑の裏の文字を揮毫した人物はだれか。 |
| 1 高浜虚子 2 清水崑 3 川端康成 4 横山隆一 |
| 荏柄天神社のかっぱ筆塚は漫画家清水崑が絵筆を納めるために建立。 裏側の「かっぱ筆塚」の文字は川端康成が揮毫。 |
答 3
 |
| 荏柄天神社では、毎年10月、かっぱ筆塚を建立した清水崑を偲ぶ絵筆塚祭が行われています。 絵筆塚は、清水崑の遺志を継いだ横山隆一らが建立したもの。 |
| (44) | 円覚寺について,次の説明文の内容に誤りを含むものはどれか。 |
| 1 | 寺名の由来は,起工の際,地中から「円覚経」を納めた石櫃が掘り出されたことによる。 |
| 2 | 円覚寺の塔頭黄梅院は,夢窓疎石の塔所で門弟の方外宏遠が1354年(文和3・正平9)に開創したのち,足利義詮の遺骨が分骨され,足利氏の菩提寺の性格を帯びた。 |
| 3 | 鐘楼には物部国光が鋳造,北条貞時が寄進した洪鐘があり,建長寺,常楽寺とともに鎌倉三名鐘の一つで,国宝に指定されている。 |
| 4 | 開山が著した代表的な墨蹟「法語規則」は国宝に指定され,衆僧が修行するうえでの心 構えを記した法語と僧堂での取り決めや罰則をしたためた規則の二幅から成る。 |
| 円覚寺の開山は無学祖元。 国宝の「法語規則」は建長寺開山の蘭渓道隆が著したもの。 |
答 4
| 円覚寺は、八代執権北条時宗が建立した禅寺。 塔頭正続院の舎利殿は、源実朝が宋より請来した仏舎利が納められている建物で、鎌倉で唯一の国宝建築物。 鎌倉三名鐘の一つ洪鐘は、九代執権北条貞時が江の島に参籠したことで鋳造に成功したという鎌倉最大の梵鐘(国宝)。 2023年(令和5年)10月29日、洪鐘祭が開催されました。 |

| (45) | 巽神社について,次の説明文で内容に誤りを含むものはどれか。 |
| 1 | 起源は,801 年(延暦 20),蝦夷征討に向かう途中の坂上田村麻呂が扇ヶ谷に勧請したのが始まりとされる。 |
| 2 | 1049年(永承4),源頼義が社殿を改修したと伝えられる。 |
| 3 | 壽福寺の鎮守として崇められ,寺の「巽」の方角(南東)に位置するところからこの名がついたという。 |
| 4 | 境内には江戸時代の銘が刻まれた手洗石や石燈籠などがある。 |
| 巽神社は、坂上田村麻呂が葛原ヶ岡に勧請したのを始まりとします。 |
答 1

| 801年(延暦20年)、坂上田村麻呂は、蝦夷討伐を行い、翌802年(延暦21年)、指導者のアテルイとモレを降伏させています。 坂上田村麻呂が建立した京都の清水寺には、アテルイ・モレの碑が建てられています。 平泉の達谷窟毘沙門堂は、蝦夷討伐の際に坂上田村麻呂が建てたという堂。 |
| 寺院・神社について関連あることがらの組み合わせとして誤っているものを 1 ~ 4 から選びなさい。 |
| (46) | 寺社とそのゆかりの碑・墓・塚 |
| 1 龍寳寺-松平信綱の碑 2 建長寺西来庵-蘭渓道隆の墓 3 仏行寺-源太塚 4 白山神社-酔亀亭天広丸の歌碑 |
| 龍寳寺には新井白石の碑があります。 第18回鎌倉検定1級に出題されています。 |
答 1
| (47) | 掲額と関係の深い人物 |
| 1 | 九品寺の「内裏山」「九品寺」の額 -新田義貞 |
| 2 | 光明寺山門の「天照山」の扁額 -後花園天皇 |
| 3 | 本覚寺の「東身延」の額 -徳川慶喜 |
| 4 | 円覚寺の「円覚興聖禅寺」の額 -伏見上皇 |
| 本覚寺の「東身延」の額は松平定信。 |
答 3

| 「包丁正宗」は、荏柄天神社に伝来した名刀。 本覚寺の「東身延」の額を書いた松平定信の『集古十種』にも収録されています。 |
| 鎌倉検定過去問~東身延の額:五郎入道正宗と松平定信~ |
| 寺院・神社について,次の説明文の〔 〕に最も適当なものを 1 ~ 4 から選びなさい。 |
| 現在,鎌倉で唯一の尼寺である〔 (48) 〕の開基は,扇ヶ谷上杉氏の家宰であった〔 ㊾ 〕 の4代目の子孫で,その縁から〔 (48) 〕は,〔 (49) 〕の邸宅址に建立された。 また,その開基が〔 (50) 〕藩の初代藩主徳川頼房の猶母であり,歴代藩主の娘が寺の住職を務めていたので,江戸藩邸に準ずるものとなった。 本堂脇には,〔 (49) 〕の雨宿りにまつわる和歌の伝説ゆかりの花〔 (51) 〕が植えられている。 |
| (48) |
| 1 東慶寺 2 太平寺 3 英勝寺 4 高松寺 |
| (49) |
| 1 太田道灌 2 長尾定景 3 太田道真 4 長尾景虎 |
| (50) |
| 1 尾張 2 水戸 3 紀州 4 川越 |
| (51) |
| 1 ツバキ 2 カイドウ 3 サザンカ 4 ヤマブキ |
答
(48) 3
(49) 1
(50) 2
(51) 4
 |
| 英勝寺は「水戸さまの尼寺」と呼ばれました。 開基の英勝院尼は、扇谷上杉氏に仕えた太田道灌から数えて四代の孫康資の娘。 徳川光圀が建立した祠堂は英勝院の廟所。 |
| 裏山には太田道灌の首塚があります。 ヤマブキは、にわか雨にあった道灌が立ち寄った民家の娘が差し出した花。 |
| 甘縄神明神社は〔 (52) 〕が草創し,豪族の〔 (53) 〕が建立した鎌倉で最も古い神社とされている。 源頼義が当社に祈願して子宝(のちの〔 (54) 〕)を授かったことから,源氏との縁が深い神社として信仰されている。 作家川端康成は長くこの神社の近くに住んだこともあり,小説『〔 (55) 〕』にはこの辺りが描かれている。 |
| (52) |
| 1 空海 2 行基 3 坂上田村麻呂 4 光明皇后 |
| (53) |
| 1 藤原鎌足 2 藤原不比等 3 鎌倉権五郎景政(正) 4 染屋時忠 |
| (54) |
| 1 源義家 2 源頼政 3 源義光 4 源為義 |
| (55) |
| 1 伊豆の踊子 2 雪国 3 山の音 4 古都 |
答
(52) 2
(53) 4
(54) 1
(55) 3
| 甘縄神明神社は、僧行基の草創によって、由比の長者と呼ばれた染屋時忠が神明宮と神輿山円徳寺を建立したのがその始まりと伝えられています。 染屋時忠は奈良の東大寺を開いた良弁の父という説も。 聖武天皇の勅願により建立されたという関東総国分寺としての清浄泉寺(現在の高徳院)は時忠が奉行したのだとか。 |
 |
| 河内源氏二代棟梁の源頼義は、甘縄神明神社に祈願して嫡男の義家を授かったのだと伝えられ、義家は京都の石清水八幡宮で元服したことから「八幡太郎」と呼ばれました。 川端康成記念会が設立された旧川端康成邸は、小説『山の音』の舞台となりました。 |
|
|

第18回2級トップ

(3級・2級・1級の問題と解説)
| ★鎌倉検定の受検お申し込みは 鎌倉商工会議所ホームページへ |
(鎌倉情報トップ)
|
|