 |

|
|
七福神とは・・・。
| 大黒天・恵比寿・毘沙門天・弁財天・福禄寿・寿老人・布袋和尚の七人の福徳の神のこと。 福禄寿・寿老人は同じであるとして、吉祥天を入れることもあります。 |

| 七福神信仰は室町時代後期ごろから、お正月行事として庶民の間で広まったと言われています。 七福神信仰の発祥は京都(参考:都七福神)。 鎌倉・江の島七福神めぐりは、1982年(昭和57年)から始められました。 新春に巡拝すると 「七難即滅 七福即応」 の御利益があるといわれている七福神めぐりですが、正月に限らず1年を通して参詣することができます。 源頼朝が武家政権を樹立し、中世の政治の中心となった鎌倉の史跡巡りを兼ねて七福神を巡るのも鎌倉の楽しみ方の一つかもしれません。 江の島も鎌倉の武家政権とは大きく関わった島です。 源頼朝は弁財天を勧請し、源実朝は江島神社の辺津宮を創建しています。 |
| ※ | 鎌倉・江の島七福神巡りは、弁財天が二ヶ所ありますので、合計八ヶ所を巡ります。 |
2025年(令和7年)は巳年!
| 巳(蛇)は弁財天の使い。 蛇が弁財天に願いを届けてくれる! 鎌倉江の島七福神には弁財天が二ヶ所。 |
| 布 袋 尊・・・浄智寺 〜福徳円満〜 |
| 中国の禅僧布袋和尚を神格化したもの。 |
 |
| 浄智寺の布袋尊は、境内奥の「やぐら」の中に置かれた等身大の石像。 お腹を撫でると元気がもらえるそうです。 |
| 弁 財 天・・・鶴岡八幡宮 〜芸能成就〜 |
| インドでは吉祥天とともに最も尊崇された女神。 |
| 鶴岡八幡宮の弁財天は鎌倉独特の彫刻技法の「裸弁財天」。 武運長久・大願成就の福神。 |

(木造弁財天坐像)
| 鶴岡八幡宮の木造弁財天坐像は、鎌倉独特の裸像彫刻で重要文化財に指定されています。 かつては、源氏池の旗上弁財天社に置かれていましたが、現在は鎌倉国宝館に寄託されています。 2025年1月7日からの展示会「新春は 国宝館へ はつもうで」に展示される予定です。 |
| 毘沙門天・・・宝戒寺 〜勝運来福〜 |
インドの財産を守る神。
| 毘沙門天は多聞天とも呼ばれ、帝釈天に仕える四天王の一人。 病魔退散・財宝富貴の福神。 本堂に左手に安置されています。 |
| 寿 老 人・・・妙隆寺 〜長寿延命〜 |
中国宋代の人。長寿を授ける神。
 |
| 妙隆寺の本堂前の御堂に置かれているのは、欅一木造りの尊像です。 |
| 夷 尊 神・・・本覚寺 〜商売繁盛〜 |
| 唯一の日本人。漁業や商売繁盛の神。 |
| 本覚寺の夷尊神は、鎌倉幕府の守護神として源頼朝によって祀られたのが始まりといわれています。 正月には「鎌倉えびす」が行われます。 1月1日から3日が初えびす、1月10日が本えびす。 |
| 大 黒 天・・・長谷寺 〜出世開運〜 |
| 大国主命と習合して民間信仰に浸透した仏教の守護神。 |
 |
| 長谷寺の大黒堂に安置されているのは「出世開運授け大黒天」。 観音ミュージアムでは神奈川県最古の尊像を拝観することができます。 |
| 福 禄 寿・・・御霊神社 〜家禄永遠〜 |
| 中国では南極星の化身とされる神。 |
| 御霊神社の9月の例祭では、福禄寿が参加する面掛行列が行われます。 これにちなんで、宝物庫には福禄寿が安置されています。 福禄寿は泰山府君の別の姿といわれています。 泰山府君は、人間の生死・寿命や死後の審判を司る神で、仏教の閻魔大王に相当する神。 |
| 弁 財 天・・・江島神社 〜金寶富貴〜 |
| インドでは吉祥天とともに最も尊崇された女神。 |
| 江島神社の辺津宮にある八角の奉安殿には、裸弁財天で知られる「妙音弁財天」と、源頼朝が勧請したとも伝えられてきた「八臂弁財天」が安置されています。 八臂弁財天は2019年(令和元年)に国の重要文化財に指定されました。 奥津宮の石鳥居は源頼朝の寄進、辺津宮は源実朝の創建と伝えられています。 また、北条時政の龍神伝説が残され、北条貞時の円覚寺の国宝洪鐘の伝説も残されています。 江戸時代には江の島詣が盛んに行われ、江戸からの参拝者で賑わいました。 江の島入口の青銅鳥居は、新吉原の楼主が願主となって建立したものです。 |
| ※ | 江の島弁財天は、安芸の宮島、近江の竹生島とともに日本三大弁財天の一つ。 |


| 横須賀線北鎌倉駅からスタートし、江ノ島でゴールするコースが一番回りやすいコースかと思います(逆コースでも。)。 浄智寺でご朱印帳や額仕立用のご朱印専用和紙などを購入し、全ての神様のご朱印を頂けば達成感も生まれます。 特に、頂いたご朱印を額にするとかなり豪華なものになります。 |
〜初夢と七福神の宝船〜

| 初夢は1月1日から2日にかけて見る夢。 七福神の宝船の絵に、 「永き世の遠の眠りのみな目ざめ波乗り船の音のよきかな」 (なかきよのとおのねふりのみなめさめなみのりふねのおとのよきかな) という回文を書いて枕の下に置き、回文を3回読んで眠りに就くと吉夢が見られるといいます。 もし、悪い夢を見てしまった場合は、 その宝船の絵を川に流して邪気を祓い流すだそうです。 |
(京都で始まった七福神信仰)

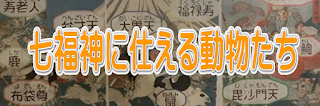
| 七福神発祥の地 京都 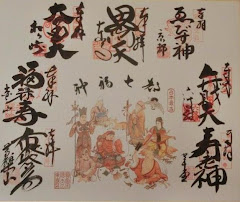 |
源義経伝説と 七福神 |
鎌倉江の島七福神MAP
| 大きい地図を見るには・・・ 右上のフルスクリーンをクリック。 |

(鎌倉の名所・名数)
(鎌倉情報トップ)
 |
 |
 |
 |
 |
|
|