 |
 |
 |
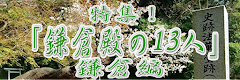 |
〜義経逃亡と守護・地頭の設置〜
〜義経都落ち〜
| 1185年(文治元年)10月18日、後白河法皇が源義経に「頼朝追討の宣旨」を発すると、鎌倉の源頼朝は、10月29日、自ら出陣し、11月1日には黄瀬川宿に到達します。 一方、思うように兵の集まらない京の義経は、11月3日、都を落ち、海路、九州へ逃れようとしますが、11月6日、摂津国大物浦で難破してしまいます。 その後の義経は姿をくらまします。 11月8日、義経が都を落ちたことを聞いた頼朝は、鎌倉へ引き上げますが、京には東国軍が次々に上り、朝廷に対して強硬な態度で望みます。 この事態に驚いた後白河法皇は、今度は頼朝に「義経・行家追討の院宣」を下しました。 頼朝は、後白河法皇の弁解に対する返書に 「日本国第一の大天狗はさらに他に居申さぬ」と記したといいます。 |
| ※ | 義経の都落ちには叔父の行家も同行していましたが、行家は1186年(文治2年)5月12日、和泉国に潜んでいるところを討ち取られています。 |
〜守護・地頭の設置〜
| 11月12日、頼朝は、朝廷に対し守護・地頭の設置を要求する事を決めます。 『吾妻鏡』によると、義経の京都退去への対策を考える頼朝に、大江広元が「守護・地頭」を設置する案を献策し、頼朝がこれを採用したのだといいます。 |
〜大江広元の守護・地頭設置案〜
| 世も末で、無法者が勢い盛んになる時です。 反逆する者がなくなることはないでしょう。 東海道は頼朝公が支配して治まると思われますが、地方での反乱が必ず起こります。 それを鎮めるためにその都度兵を派遣していたのでは、人々の負担となり、国費を無駄に遣うことになるので、 この機会に諸国に権力を及ぼすようにし、国衙、荘園ごとに守護・地頭を設置すれば、反乱を恐れることはないでしょう。 早く朝廷に守護・地頭の設置を申し入れすべきです。 |
| この案を受け入れた頼朝は、北条時政に千騎をつけて入京させ、 国ごとに「守護」を、全ての荘園・国衙領を管理するために「地頭」を任命し、「兵粮米」として反当たり五升を徴収する という要求を朝廷に突き付けます。 これを受け入れた朝廷は、11月29日、「義経・行家の捜索・逮捕」、「守護・地頭の設置」、「兵粮米の徴収」を認めました(文治の勅許)。 これにより、頼朝は、自らの命で動かすことのできる御家人を全国に配置することになります。 |

| ※ | 1186年(文治2年)3月12日、頼朝の推挙によって九条兼実が摂政となっています。 |
〜誅殺された舅の河越重頼〜
| 11月12日、義経の正室郷御前の父河越重頼が、義経の舅という理由で所領を没収され、誅殺されています。 義経と郷御前は、前年に頼朝の命で結婚していました。 重頼が誅殺されたことで、重頼が就いていた「武蔵国留守所惣検校職」は畠山重忠が継承しています。 |
(川越市:養寿院) |
(川越市:常楽寺) |
〜捕らえられた静御前〜
| 11月17日、義経の妾・静御前が吉野山で捕えられます。 静御前は義経の都落ちに同行し、大物浦で難破した後も行動を共にしていましたが、吉野山で義経と別れたと伝えられています。 のちに鎌倉へ送られた静御前は、頼朝の前で舞を披露することになります。 |
| 吉野山で義経と別れた静御前は、金峯山寺(蔵王堂)の僧兵に捕まり、鎌倉へ送られました。 |
〜大阪に残された義経の足跡〜
 (四天王寺) |
 |
| 吉野山に逃げ込む前に、義経は四天王寺と住吉大社に立ち寄っているのだとか。 |
〜義経を匿った比叡山と興福寺〜
| 比叡山延暦寺と興福寺の僧兵は、頼朝の追手から逃げる義経を匿っていました。 |

勝長寿院の創建 |
義経を慕う静の舞 |

|
|
(鎌倉情報トップ)