 |
 |
 |
 |
第6回鎌倉検定試験2級
《祭り・行事の問題》
|
|
| 祭り・行事に関する記述について、最も適当なものを1〜4から選びなさい。 |
| (81) | 毎年7月15日に、建長寺で施餓鬼会を二度行うのはだれのためか。 |
| 1 源義経 3 梶原景時 |
2 比企能員 4 和田義盛 |
| 建長寺の三門梶原施餓鬼会は、あるときの施餓鬼会に蘭渓道隆の前に現れた梶原景時の亡霊のために行われます。 |
答 3

| (82) | 鶴岡八幡宮の七夕祭は、宮中で行われていたやり方を伝えた京都冷泉家の祭を参考に行っているが、五色に染められた絹糸や絹布、梶の葉などが備えられる場所はどこか。 |
| 1 本宮 3 若宮 |
2 舞殿 4 旗上弁財天社 |
答 2

| (83) | 光明寺の十夜法要を勅許した天皇はだれか。 |
| 1 後花園天皇 3 後深草天皇 |
2 後嵯峨天皇 4 後土御門天皇 |
| 光明寺の十夜法要は、1495年(明応4年)、後土御門天皇から勅許されました。 |
答 4
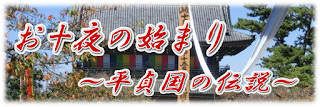
| (84) | 虚空蔵堂で、虚空蔵菩薩が開帳され、護摩が焚かれ読経が行われるのは、年何回か。 |
| 1 | 1月にみの年1回 |
| 2 | 1月、9月の年2回 |
| 3 | 1月、5月、9月の年3回 |
| 4 | 1月、4月、7月、10月の年4回 |
| 毎月13日は虚空蔵菩薩の縁日。 虚空蔵堂の護摩焚き供養は、1月、5月、9月の13日に行われています。 |
答 3
| (85) | 毎年1月1日に鶴岡八幡宮で行われる神楽始式で、地元小学生により奉仕されるのは何か。 |
| 1 鎌倉木遣唄 3 人長の舞 |
2 八乙女の舞 4 鎌倉天王唄 |
| 「木遣唄」は鶴岡八幡宮の「手斧始式」や宝戒寺の「太子講」などで歌われます。 「人長の舞」は鶴岡八幡宮の「御鎮座記念祭」で舞われます。 「天王唄」は、材木座海岸の「潮神楽」などで歌われます。 鶴岡八幡宮の「神楽始式」では八乙女の舞が奉仕されます。 |
答 2
| 祭り・行事について関連あることがらの組み合わせとして誤っているものを1〜4から選びなさい。 |
| (86) | 神社の例祭と行われる時期 |
| 1 | 鎌倉宮例祭−8月20日 |
| 2 | 荏柄天神社例祭−7月25日 |
| 3 | 八雲神社例祭(大町)− 7月7日〜14日の間の土曜日から3日間 |
| 4 | 御霊神社例祭(坂ノ下)−海の日 |
| 坂ノ下の御霊神社の例祭は、祭神の鎌倉権五郎景政の命日に当たる9月18日に行われます。 海の日に行われるのは境内社の石上神社の例祭(御供流し)。 |
答 4
| (87) | 故人の遺徳を偲ぶ行事行われる寺社 |
| 1 義経まつり−満福寺 2 河村瑞賢供養−円覚寺 3 文墨祭−白旗神社 4 清正公祭−妙法寺(大町) |
| 河村瑞賢は、建長寺の裏に別荘があったといわれ、建長寺には墓が建てられています。命日である6月16日に法要が営まれます。 |
答 2
| 祭り・行事について、次の説明文の[ ]に最も適当なものを1〜4から選びなさい。 |
| 武家の古都にふさわしい行事はその見事な武芸を披露することである。 例えば、春恒例の「鎌倉まつり」の最終日や鶴岡八幡宮の秋の例大祭で行われる[ (88) ]や、[ (89) ]に[ (90) ]で行われる草鹿はいずれも武家の嗜みである弓矢の技を競うものである。 また、弓矢は悪霊などの穢れを祓う神聖なものでもある。新年1月5日に鶴岡八幡宮で行われる除魔神事は、鎌倉時代から続く武士の事始めの儀式で、裏に「[ (91) ]」の文字が書かれた大的を弓矢で射て災いや穢れを祓う。 |
| (88) | |
| 1 流鏑馬 3 笠懸 |
2 巻狩 4 犬追物 |
| (89) | |
| 1 2月8日 3 5月5日 |
2 4月13日 4 8月10日 |
| (90) | |
| 1 甘縄神明神社 3 荏柄天神社 |
2 鎌倉宮 4 御霊神社 |
| (91) | |
| 1 邪 3 魔 |
2 悪 4 鬼 |
 |
答
| (88) 1 (89) 3 (90) 2 (91) 4 |
| 立秋の前日から3日間(年によっては4日間)、鶴岡八幡宮で行われるぼんぼり祭は、鎌倉在住の著名人の書画が描かれたぼんぼりが境内に約[ (92) ]基掲揚され、夕暮れとともに点火される夏の風物詩である。 この間、立秋の前日に行われる夏越祭では、夏の邪気を祓うため、源平池ほとりの神事のあと、[ (93) ]を行って無病息災を祈願する。翌日には、二十四節気の一つである立秋祭が行われる。夏の間の無事を感謝し、実りの秋の訪れを奉告する。神前には神域で生育された[ (94) ]が供えられる。最終日、鎌倉幕府第3代将軍源実朝の誕生日である[ (95) ]には、和歌に長けた実朝の遺徳を偲んで、献華、献茶、短歌・俳句の会が催される。 |
| (92) | |
| 1 100 3 300 |
2 200 4 400 |
| (93) | |
| 1 茅の輪くぐり 3 獅子舞 |
2 湯立神楽 4 面掛行列 |
| (94) | |
| 1 蝶 3 鈴虫 |
2 鯉 4 蛍 |
| (95) | |
| 1 8月3日 3 8月9日 |
2 8月6日 4 8月12日 |

答
| (92) 4 (93) 1 (94) 3 (95) 3 |
|
|

第6回2級トップ

(3級・2級・1級の問題と解説)
| ★鎌倉検定の受検お申し込みは 鎌倉商工会議所ホームページへ |
(鎌倉情報トップ)
|
|