 |
 |
 |
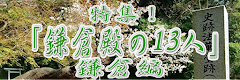 |
〜木曽義仲追討〜
| 1183年(寿永2年)閏10月、木曽義仲と対立していた後白河法皇は、源頼朝を上洛させるため、頼朝を元の官職である従五位下左兵衛佐に戻し、「東海・東山両道における頼朝の支配権」を認めます(寿永二年十月宣旨)。 これによって、これまで反乱軍として扱われていた鎌倉軍は、朝廷から認められる軍となりました。 さっそく頼朝は、その権限を行使し、翌11月に入ると、木曽義仲の動向を探るため、弟義経を近江国へ派遣します。 一方、後白河法皇に見放され、頼朝の上洛を恐れる都の義仲は、11月19日、後白河法皇の法住寺殿の焼き討ちし、12月には頼朝追討の院宣を強要、翌年1月には征東大将軍に任命されました。 これに対し頼朝は、弟範頼に義仲追討を命じ、大軍をつけて鎌倉を出発させます。 そして、1月20日、範頼が瀬田から、義経が宇治から京を攻撃したことで、義仲は惨敗を喫します。 義仲はわずかな兵ととともに京を脱出しますが、1月20日、範頼の大軍に攻められ、近江国粟津で討死しました。 |
(京都市東山区)
| 三十三間堂は、後白河法皇の院御所法住寺殿の一画に建てられました。 |
(宇治市)
| 宇治川の戦いでは、佐々木高綱と梶原景季が先陣争いを繰り広げました。 |
(大津市)
| 範頼が進軍した橋 |
(大津市)
| 義仲寺は、粟津の戦いで討たれた義仲が葬られた場所と伝えられています。 |
(義仲寺)
(京都:八坂の塔)
| 義仲の首は六条河原に晒された後、家臣の手で葬られたのだと伝えられ、八坂の塔に首塚が建てられています。 |
(義仲寺)
| 木曽義仲の愛妾・巴御前の供養塔。 |
(大津市)
| 今井兼平は義仲の重臣。 粟津の戦いで義仲とともに壮絶な最期を遂げました。 |
(長野県木曽町:徳音寺)
| 義仲が育った木曽の徳音寺には、義仲・母の小枝御前・巴御前・樋口兼光・今井兼平の墓が建てられています。 |
(京都:時代祭)
上総広常の暗殺 |
木曽義高の誅殺 |

|
|
(鎌倉情報トップ)