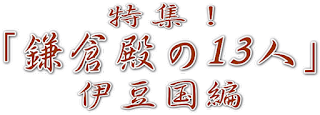富岡製糸場
『青天を衝け』渋沢栄一
|
|

(画像提供 富岡市)
| 群馬県富岡市の富岡製糸場は、1872年(明治5年)に開業した日本初の本格的な器械製糸の工場。 主要な輸出品であった生糸の品質向上と増産のため、明治政府により官営として設立された。 2014年(平成26年)、「富岡製糸場と絹産業遺産群」として世界文化遺産に登録されている。 |

(画像提供 富岡市)
~建設に貢献した深谷の三大偉人~
| 富岡製糸場の設立は、明治政府の伊藤博文(大蔵少輔)や渋沢栄一(大蔵省租税正)が担当となって進められた。 特に、渋沢栄一は、農家出身で蚕桑(桑を育てること)や蚕種(蚕の卵)に詳しかったこともあって、富岡製糸場設置主任に任命されている。 工場建設の現場を取り仕切ったのは尾高惇忠。 資材調達を任されたのは韮塚直次郎。 渋沢栄一・尾高惇忠・韮塚直次郎は、いずれも武蔵国榛沢郡(現在の埼玉県深谷市)で生まれ、深谷の三大偉人と呼ばれている。 富岡製糸場の操業が開始されると、尾高惇忠は場長に、韮塚直次郎は社員食堂の運営を担当した。 |

女工館
(画像提供 富岡市)
| 場長となった尾高惇忠は、特に工女の教育に重点を置き、一般教養の向上と場内規律の維持につとめた。 ただ、工女の募集は困難を極めた。 その理由は、フランス人技師の飲む赤ワインが若い娘の血と誤解されたから。 工女の募集は生き血を絞るためという噂が流れる中、惇忠の長女の勇(ゆう・14歳)が最初の工女となると、松村くら(17歳)をはじめとする少女5人が志願。 さらに松村くらの祖母わし(62歳)も志願し、工女取締役として富岡製糸場の繁栄を支えたのだという。 |
(渋沢栄一生地)

(韮塚直次郎奉納)
| 富岡製糸場の主要な建築材料は煉瓦。 韮塚直次郎は、地元の瓦職人たちを束ね、外国人技師バスティアンなどからアドバイスを受けながら、粘土探しから始めた。 そして、富岡に近い笹森稲荷神社(現在の甘楽町福島)付近の畑から煉瓦に適した粘土を発見し、その周辺に窯を設けて、煉瓦を焼き上げることに成功したのだという。 富岡製糸場完成後の1875年(明治8年)、事業の成功に感謝した直次郎は、笹森稲荷神社に大絵馬を奉納。 1880年(明治13年)には、地元深谷の永明稲荷神社にも同様の大絵馬を奉納してる。 |

富岡製糸場行啓
(明治神宮御鎮座百年祭パネルより)
| 1873年(明治6年)、宮中養蚕を復活させた昭憲皇太后(明治天皇の皇后)は、英照皇太后(孝明天皇の女御)とともに富岡製糸場を行啓している。 |
~富岡製糸場と絹産業遺産群~
| 田島弥平旧宅は、瓦屋根に換気設備を取り付けた近代養蚕農家の原型。 田島弥平は、昭憲皇太后が始めた宮中養蚕の世話役を務めている。 |
 高山社跡 |
 荒船風穴 |
| 高山社跡は、日本の近代養蚕法の標準「清温育」を開発した場。 荒船風穴は、自然の冷気を利用した日本最大規模の蚕種貯蔵施設。 |
2021年大河ドラマ





富岡製糸場
(画像提供 富岡市)
| 群馬県富岡市富岡1-1 上信電鉄「上州富岡駅」から徒歩15分 |
富岡製糸場・笹森稲荷神社
| 大きい地図を見るには・・・右上のフルスクリーンをクリック。 |
|
|
2022年NHK大河ドラマ